こんにちは、黒帯兄さんこと八木橋ショーガックです!
今回は、僕の歌声に欠かせない「共鳴」と「フォルマント」の話をしてみようと思います。
ボイストレーニングって、「お腹から声を出せ!」とか「口を大きく開けろ!」っていう指導を受けることが多いけど、実はもっと大事なのは響き=共鳴のコントロールなんです。
そしてそのカギを握るのが、「軟口蓋(なんこうがい)」と「フォルマント」の使い分け。
ちょっと難しく聞こえるかもしれないけど、小学生でもわかるように解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください!
もくじ
🎤 響きを変えるカギは「軟口蓋のポジション」
まず、僕の基本的な発声スタイルは 軟口蓋を上げた状態がベースです。
どういうことかというと…
-
軟口蓋を上げることで鼻に抜ける空気の通り道を閉じる
-
すると、口の中と喉(咽頭)で響きが強くなる
-
結果、太くて芯がある声が出やすくなる
たとえば「仮面ライダーBLACK RX」みたいな、直線的でビームのような声が必要な曲では、これがめちゃくちゃハマります。
🧠 でも、それだけじゃない!状況に応じて「軟口蓋を下げる」こともある
そうなんです。いつも軟口蓋をガチッと上げているわけじゃありません。
たとえば…
-
ウィスパーボイスや繊細なフレーズ
-
やわらかく、少し鼻にかかったような音色を出したいとき
こういうときは 軟口蓋をやや下げて、鼻に抜ける共鳴(鼻腔共鳴) を取り入れます。
これを意識的にやっていると、「黒帯兄さんって鼻腔共鳴が強いですよね」と言われることがあるんです。
実際、柔らかく聴こえるように演出してるって感じですね。
🎵 代表的なカバー曲での使い分け例
以下は、僕がYouTubeにアップしている人気カバー曲の中で、軟口蓋の使い方と共鳴の傾向を分析した表です!
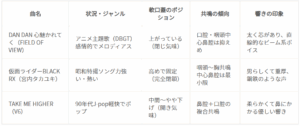
In this way, by aiming for reducing the distance in a "Jun-zuki",曲によって響きをデザインしているんです。
🔬 さらに進化するなら「フォルマント周波数」を意識しよう!
軟口蓋の上げ下げは、「音の入り口」をコントロールしてるだけ。 でも本当に大事なのは、その先にある「フォルマント周波数(F1〜F3)」です。
フォルマントとは?
簡単に言うと、「声のどこがどんなふうに響いているか」を示す周波数の帯域のこと。
これをコントロールすることで、音の太さ・抜け・艶・透明感が自由に作れます。
🎧 フォルマントごとの特徴
フォルマント周波数(F1、F2、F3)分類表
F1=Green
F2=Red
F3=Blue
※RGB(Green、Red、Blue)は、分かりやすくするための
ショーガック・オリジナルのネーミングです。
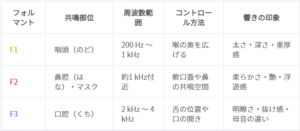
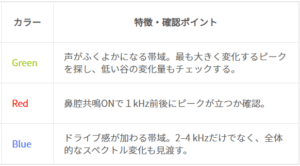
🎙️ 僕の歌唱での実践ポイント
-
感情的で直線的なパート:F1とF3を強めにコントロール(咽頭・口腔)
-
柔らかく聴かせたいパート:F2を意識的に取りにいく(鼻腔)
-
音の芯と抜けを両立したいとき:F2+F3のバランスを整える
実際に歌いながら、**スペクトラムアナライザー(スペアナ)**でF1〜F3の分布を見て、
響きをチューニングすることもあります。
響きをチューニングすることもあります。
これはもう「ボーカル=音響設計」だと思ってます。
📌 僕が意識していることのまとめ

✅ 結論:器官を意識するな、音響を意識せよ!
軟口蓋はとても重要な部位だけど、それはあくまで**「響きの入り口」。
プロとして意識すべきなのは、その先にある「フォルマント構造」と「音響的な結果」**です。
僕の声が「芯があるのに柔らかい」「太いのに透き通っている」と言われるのは、
この響きの設計を日々研究し、訓練し続けているからなんです。
この響きの設計を日々研究し、訓練し続けているからなんです。
✍️ 最後に…
この話を読んで、「自分の歌声ももっと響きをコントロールしたい!」と思った人は、
ぜひ自分の歌声を録音して、スペアナ(FrequenSee – スペクトラムアナライザー)で見てみてください。
ぜひ自分の歌声を録音して、スペアナ(FrequenSee – スペクトラムアナライザー)で見てみてください。
そして、自分の歌声のF1・F2・F3の分布を分析することで、どんな共鳴が足りないのか、逆に何が強すぎるのか、ハッキリ見えてきます。
それを少しずつ整えていくことが、「あなたらしい声=唯一無二の音色」を作る第一歩です。
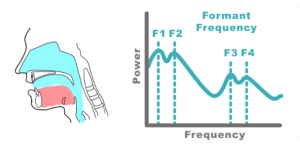
↑↑↑
※画像はこちらからお借りしました。

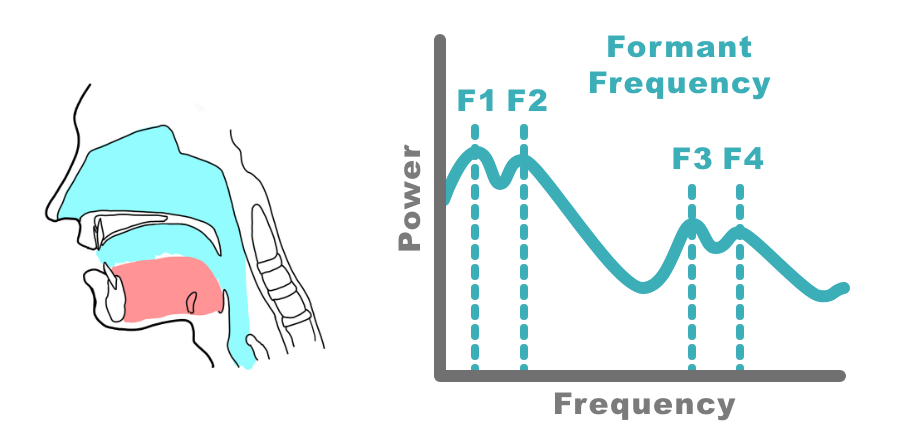
Stay connected